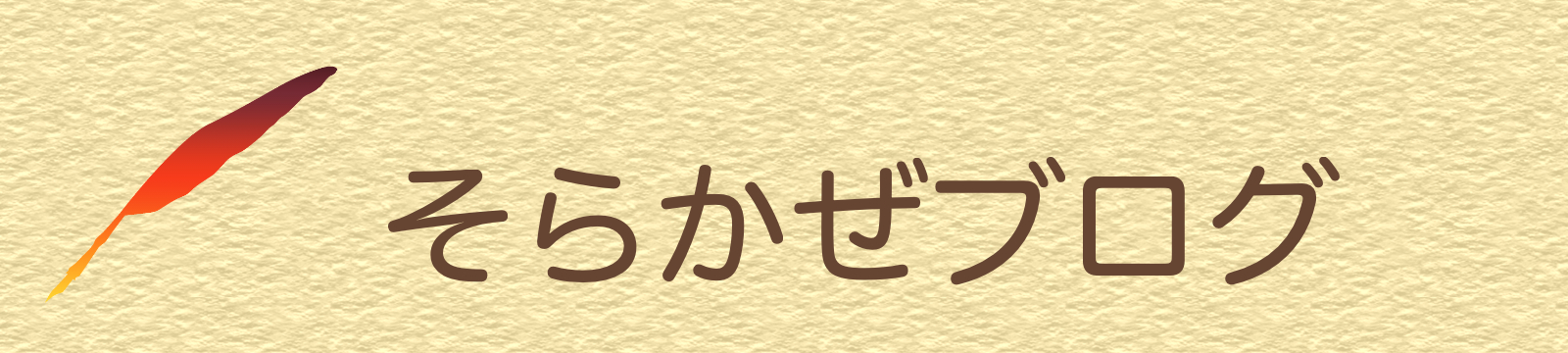わたしも、新入社員のときは、電話応対には戸惑いました。
電話を取るといっても、自分にかかってくるわけがありません。社内の誰かにかかってきた電話を取り継ぐわけですが、そんなにすぐに同じ部署の人の名前と顔が一致するわけがありません。大企業でしたので、ワンフロアに大勢がいます。保留ボタンを押して、転送するのにも手間取ります。もちろん、こんなものは慣れなので、場数を踏むしかありません。
それに、今とは違って、固定電話が主流の時代だったので、家庭でもまだ固定電話を使っていました。電話を取り次ぐということ自体はやったことがないわけではありません。
それに対して、最近は、個々人が電話を持っていますので、そもそも取り次ぐということがありません。なので、昔とは事情がちょっと違う気がします。
また、自分のスマホに知らない番号からかかってきたら、100%出ません。ネットで電話番号を調べて、相手方がはっきりしたらかけ直します。企業でも、詐欺に引っかかったという話があるので、電話応対にも慎重になる必要ができてきました。
もちろん、電話にもメリットがあって、まず、話がスムーズに進む、というのがあります。メールやチャットではやはり意思疎通に限界があります。ビデオ会議もありますが、いちいち設定が面倒です。電話は一方的に相手の時間を奪うという問題がありますが(都合の悪いときにかけてしまう)、やはり便利です。
まともに電話を取れない若者たち ビジネス・コラムニスト ピリタ・クラーク
米国の採用担当者が先日オンライン上に投稿したコメントが、あっという間に異例の閲覧数を獲得した。
電話を多用する採用担当者が日常で気づいたことを投稿しただけだ。いわく、最近では働く20代の若者の多くは電話に出ても「もしもし」とも「やあ」とも言わず、まったくの無言だという。
戸惑い気味の採用担当者は「息遣いや背後の騒音が聞こえるだけで、彼らはまずこちらが『もしもし』と言うのを待っている」と投稿した。
2025年7月28日 日本経済新聞