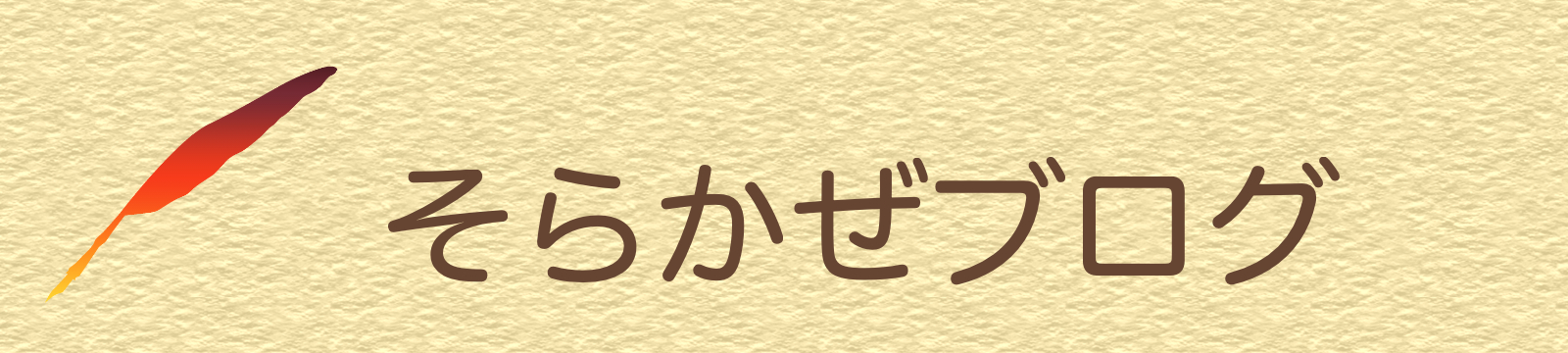Intel製MacBook Pro2017にUbuntuを入れたのですが、どうもバッテリー周りの挙動がおかしいことに気付きました。コンセントに繋いでいるのに、バッテリーが充電されず、どんどん減っていくので、電源管理がどうなっているのか心配になってきました。
当初は、Ubuntuをクリーンインストールしてしまったので、macOSで確認することもできません。仕方なく、macOSとのデュアルブートに路線変更することにしました。
ここからが苦難の道のりになってしまいました。
せっかく入れたUbuntuを消し去り、macOSをリカバリーします。
Time Machineからの復旧
Time Machineから復旧するには、macOS Venturaが入っていないといけないということで、「option+command+R」を同時に押しながら電源を入れます。
まずはディスクユーティリティを使ってディスクをAPFSでフォーマットしないと認識してくれません。ディスクが認識できるようになったらOSを入れ直します。
OSをインストールしたら、移行アシスタントを使って復旧します。
ちなみに、一度はこの移行アシスタントで復旧しました。MacBookProのディスク容量が256GBしかありません。空き容量が130GBは確保できそうなのですが、なぜかインストール可能領域が80GBになっています。なぜなのか、ディスクユーティリティで詳細を見ると、「パージ可能領域」というのが大半を食ってしまっています。
このパージ可能領域を強制的に開放する方法があるので、それを使って空き容量を増やすことができたのですが、不要なアプリもデータも消したのに130GBも食っているのは解せないので、移行アシスタントを使わずに、macOSのみを再度クリーンインストールすることにはなりました。AppleIDにも接続せずに単純にOSのみを入れたら、使用領域はわずか9GBでした。
パージ可能領域を強制的に開放する方法
パージ可能領域は、イメージとしては、macOSによって優先的に予約されている領域なのですが、ディスクの空き容量が少なくなると自動的に開放され、ディスク空き容量を増やします。この性質を利用します。つまり、ディスクにサイズの大きなファイルを強制的に書き込めば、パージ可能領域が開放されます。
この作業はターミナルで簡単に実行できます。
流れとしては、デスクトップに「largefile」というフォルダを作成します。このフォルダ内に巨大なファイルを作成します。
%dd if=/dev/random of=~/desktop/largefiles/largefile bs=15m適当なところでCtrl + Cキーを押して生成をストップします。次に、以下のコマンドを実行します。ファイル名を変える必要があります。ファイル名を同じにすると上書きしてしまい、意味がなくなってしまいます。次々に巨大サイズのファイルを作成してディスクを満杯にする作戦なので、満杯になるまでファイル数を増やしていきます。
%dd if=/dev/random of=~/desktop/largefiles/largefile2 bs=15m「ディスクの容量が極端に少なくなっています」というメッセージが出てきたら、パージ可能領域が減っていることが確認できると思います。そうなったら、目的は達成しましたので、デスクトップにあるフォルダごと削除してしまいます。
実はこの方法でも、クリーンインストール並みにはならず、Linux用の領域は100GB程度しか確保できませんでした。Minicondaは消したものの、Homebrewで色々なソフトを入れていたので、手作業で領域を広げるのは時間がかかり過ぎます。そのため、最終的にはクリーンインストールを選びました。